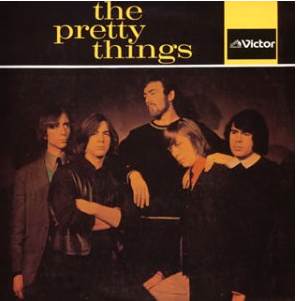【音盤銘盤】『パラシュート』 (Pretty things) '70
メンバーを一新して再始動した70年代の第1作。洗練された曲調が印象的である。
<表面>
<裏面>
前作『S.F.Sorrow』の制作が一段落した後、Pretty thingsは新たなコンセプトのアルバム作りに取り組む事になる。当時のPhil Mayのインタビューによると、
"『Parachute』は、『S.F.Sorrow』でストーリー性のあるものをやったから、次は何をやろうか?って時に見つけた答えだ。トータル性というよりはコンセプトそのものを重視した作品だね。本に喩えるならば『S.F.Sorrow』は長編小説で、『Parachute』は短編集ってところだな。このアルバムに取りかかる頃、ある興味深い現象を観察していた。都会の生活の中で起こる楽しい事や興味深いことが都会そのものを作り出していること、その一方で、当時、多くのミュージシャンや都会生活者たちが、そこでの生活に疲れ果て田舎に引っ越して農業を始めたりすることにね。"
といったことを述べている。
この風潮を反映してかアルバム全体の曲調も今までのハードロック、サイケデリックのきらびやかなものは影を潜め、フォーク、アコースティックギターを中心とした落ち着いたトーンの作品が目立つようになる。
このアルバムでもう一点注目すべき点としてジャケットのデザインが挙げられる。60年代にリリースされたアルバムのジャケットの多くは、バンドのメンバーを中心に据えて周囲にグループ名やロゴを配置するというのが定番であった。しかし、60年代の後半辺りからアルバムのコンセプトに応じてジャケットにも抽象画のようなデザイン性・芸術性を持たせる作品が増えてきた。この『Parachute』もその一つに数えられる。
夕日に映し出されたハイウェイを中心に右側(表面)には巨大なチューリップ(田園)、左側(裏面)には高層ビル(都会)を配置した比喩的なデザインである。都会と田園のコントラストを象徴的に描いたこのデザインを手掛けたのがブリティッシュロック界を代表するデザイナー・チーム、ヒプノシスである。写真とイラストを中心に据え、そこに様々なコラージュを施して立体感を演出するという画期的な手法は、まさに「アート」と呼ぶに相応しいものであった。
Pretty thingsのアルバムジャケットを手がけるのはこれが初めてであるが、両者のコラボレーションは80年代初頭のアルバム『Closs talk』まで続くことになる。
"The Good Mr. Square"〜"She Was Tall, She Was High" 「アビー・ロード」のBeatlesを彷彿とさせるゆったりしたコーラスが特徴的なナンバー。組曲にして2曲をつないでいる所もBeatlesの影響大と思われる。
"Rain" アコースティックギターを前面に押し出したブルース調の黄昏れた秀逸な逸品。アルバムジャケットの夕暮れのトーンとマッチする感じが良い。
"October 26" ワウを使って歪ませた泣くような音色のギターが光る当時のシングル曲。ギターは新加入のPeter による演奏。
このアルバムのレコーディング前にグループ創設時のギタリストDick Taylorが脱退し、オリジナルメンバーはPhil May一人となってしまった。
『Parachute』ではWally Waller,Jon Poveyによるヴォーカルでの活躍が目立つようになるが、それに応じてバンドの曲調もブルージーで荒削りなものからウエストコースト風の爽やかなトーンに変わっていったのが70年代のプリティーズの特徴である。
当時のメンバー
・Phil May – Vocals
・Vic Unitt - Guitars [album tracks only]
・Wally Waller – Bass, Guitar, Vocals
・Jon Povey – Keyboards, Vocals
・Skip Alan – Drums
・Pete Tolson - Guitars [bonus tracks only]
【音盤銘盤】『S.F.ソロウ』 (Pretty things) '68
史上初の「ロック・オペラ」となるプリティー・シングスの出世作と言えるアルバム。当時のサイケデリック指向がよく表れている大作。
従来はシングル曲の寄せ集めに過ぎなかったアルバムを60年代中盤に「コンセプトアルバム」と呼ばれる形で捉え直して一定のテーマに沿ってオリジナル曲を展開する手法を開拓したのは前にもこのブログで述べた。そして、サイケデリックブームが到来してからその発展的な形態として、全曲通してストーリーが繋がっている「ロック・オペラ」なる試みを行うグループが現れるようになった。
ロック・オペラというとThe whoの『Tommy』やThe kinksの『Arthur』が有名であるが、今回取り上げるPretty thingsの『S.F.Sorrow』がその嚆矢となる。そういった点でもっと評価されて欲しいアルバムである。
当時の制作のいきさつを述べると、Wally Waller(本作制作時のドラマー)によれば、メンバー間でのミーティングの最中に"全曲、ストーリーの繋がっている内容にしたらどうか?"と提案し、それに賛同したPhil Mayがある孤独な男の一生という物語を考え、それに合わせてそれぞれの楽曲が作り上げられていったとのことである。Philは"当時のアルバムといえば、どれもこれも10くらいの曲が入っていて、その中にシングル曲を収めなければならなかった。40分の曲が一曲だけ入ったアルバムが、なぜクラシックで認められて、ロックはポップスでは駄目なのか、って思っていた。それでオペラから影響を受けて、長い曲で構成されたアルバムを作ってみたってわけさ。"
"S.F. Sorrow Is Born" サイケデリックムーブメントの時代を反映した幻想的な曲調のオープニング。
"She Says Good Morning" Dickのファズトーンの歪んだギターとPhilの呻くようなヴォーカルスタイルは70年代のハードロックへと繋がる先進性を持っている。
"Defecting Grey" アルバム発売に先駆けて発売されたシングル。幻想的な曲調から突如ハードロック風の尖ったリズムに変わったりと目まぐるしい展開の曲。もしかしてQueenの"Bohemian Rhapsody"もこの影響を受けたのではないか?と思わせる、極めて革新的な音楽である。
"Alexander" 当時Pretty thingsとは別名義でリリースされた曲。"Electric banana"という名前で出していた事もある。
この『S.F.Sorrow』というアルバム、その内容の革新性ゆえに当時のレーベルであるEMIも発売に難色を示し、リリースが延期されてしまうという不運に見舞われてしまった。お陰でサイケデリック・ブームが下火になった頃に発売される事になり、本来後発であるはずの『Tommy』の後塵を拝すような印象を与えてしまったのは非常にもったいない事であった。近年、再結成されて"RESURRECTION"という名で本作を演奏したライヴ盤をリリースして再評価されている事は嬉しい限りである。ようやく正当な評価を受けられるようになったアルバムといえる。
【音盤銘盤】『エモーションズ』 (Pretty things) '67
プリティーズのサイケ時代に残した1枚。"Pretty things" × "サイケデリック" の解答がこのアルバムに込められている。
1967年という年はサイケデリック・ムーヴメントと切っても切れない関係にある。当時活動していたグループはこぞってサイケデリックの幻想的な世界を自分達の音楽に取り入れていたのは有名な話である。プリティー・シングスも例外ではない。ジャケットロゴの歪みに象徴的に現れている。
演奏の中でもホーンセクション、ストリングスを取り入れ、繊細な演出を施しているのが目立つ。それともう一点重要な事を挙げるならば、全曲彼らのオリジナル作で構成されている事である。このアルバムで作詞・作曲の経験値を上げて次作 ロック・オペラの嚆矢となった"S.F. Sorrow"へ繋げる事が出来た点はもっと評価されて良いところ。
"Death of a Socialite" 軽快なフォークギター、ホーンセクションを効果的に演出した曲。従来のガレージ・バンドの過激な指向は鳴りを潜めているのが印象的。
”Children” 曲間に子供達の歓声の効果音を使用。この時期らしい実験的な取り組みが見て取れる。
"Out in the Night" ホーンセクションとコーラスワークの構成が当時のBeatlesを彷彿とさせる一品。
"One Long Glance" ディストーションの施されたギターがThe whoに相通じる名曲。
”A House in the Country” アルバム発売に先立ってリリースされたシングル曲。Kinksのアルバム"Face to face"からのカヴァー。オリジナルより澄み切ったトーンが特徴的である。
”Progress” こちらもアルバム発売の前年に出たシングル。ガレージ・パンクの過激な路線に似つかわしくない軽快なポップスだが、今聞きなおしてみると決して悪くない出来である。
"emotions"というアルバム、プリティーズのファンの間でもあまり取り上げられる事の少ない一枚である。当時はグループのメンバーも作品の出来には不満だったらしく、決して高い評価を得られている作品とは言えない。確かに聞きなおしてみると演奏が稚拙な部分が目立つところではあるが、当時のサイケ時代に特有な革新的な事をしてやろう、といった意気込みが見て取れて何だか微笑ましくなる作品である。
【音盤銘盤】『ゲット・ザ・ピクチャー?』 (Pretty things) '65
R&B指向の隠れた銘盤。Pretty things内では勿論の事、60年代ロックの中で最も過小評価されているアルバムの1つ。
The Pretty things ゲット・ザ・ピクチャー?
どの業界にも「問題児」と呼ばれる人物は存在するものであるが、ご多分に漏れず60年代のブリティッシュロック界にもそういった人物は存在したのである。その名はViv Prince。今回取り上げるPretty thingsに所属していたドラマーである。この人物半端なく危険人物である。当時の奇行を挙げると、
・極度の麻薬・アルコール中毒の上に泥酔してプロボクサーと乱闘、ボコボコにされる。
・オーストラリア/ニュージーランド公演で共演したアイドル、サンディ・ショウが鼻持ちならないとして彼女の乗っていた車のシート目がけて放尿。慌てふためくサンディやスタッフを罵倒。ライヴツアーの雰囲気をブチ壊しにする。
・同じく豪/NZ公演にてステージにガソリンをまき散らし放火。公演を大混乱に陥れて急遽打ち切り、興行主に賠償請求される。おかげでオーストラリアでは未だにPretty thingsの曲が放送禁止・発売禁止になっている。
・イギリス帰国時の飛行機内にウィスキーを5本も持ち込んだ上に、瓶が割れた為に客室内にアルコールの匂いが充満。搭乗拒否される。
というように尋常でない乱暴狼藉ぶりを見せる。当然、イギリス本国のマスコミもこのスキャンダルを報じており、彼らのレコードの不買運動も起きたという。これはデビューして間もないPretty thingsにとって致命的な痛手であった。この"Viv Prince問題"の後に発売されたのが今回取り上げる"Get the Picture?"であるが、NZ公演でのスキャンダルばかりが取り沙汰されて肝心の音楽そのものには一部の音楽メディアを除き、全く触れられずに終わった何とも不運な作品である。
"You Don't Believe Me" ギターの音色がByrdsに相通じるフォーク・ロック調のナンバー。Jimmy Pageも作曲に参加しており、後年のLed Zeppelinとの関わりもこの時期から始まっている。
”Buzz the Jerk” Dickの先鋭的なギターが光る逸品。
"Get the Picture?" 1stから続くガレージ・パンクの元祖とも言える一作。Phil Mayのシャウトも健在である。
"Gonna Find Me a Substitute" Stonesのルーズなリズムに似たノリが秀逸な隠れた傑作。
"Cry to Me" Rolling Stonesのカヴァーも有名だが、このPretty thingsのバージョンも優れものである。聴き比べをしてみると面白い。
当時の乱痴気騒ぎから半世紀経過して、ごく素直にアルバムを聴き直してみると彼らの幅広い音楽性が見て取れるのが分かる。1stの先鋭的なガレージ・パンクの性急なトーンはまだまだ健在だが、渋いR&B、フォークロック、ソウルフルなバラード等、メンバーの演奏スキルの向上している所が評価できる。"Viv Prince事件"が起きていなければ、60年代のブリティッシュロック界でもっと高い評価を得られたのではないかという点が非常に悔やまれる1枚である。
【音盤銘盤】『プリティ・シングス』 (Pretty things) '65
ガレージ・バンドのパイオニアであり、ブリティッシュロックの裏街道を突っ走った老舗バンドの記念すべき1stアルバム。
2016年の音盤銘盤はPretty thingsから始める。このグループ、Beatles、Rolling Stones、Kinks、Whoといった今までこのブログで取り上げてきた"60年代ロック"と同世代のグループである。現在ではガレージ・パンクの元祖としてその名前が知られているが、それ以外にもR&B、サイケデリック、コンセプト・アルバム、ハードロック等様々な実験的な取り組みを行って主に70年代まで活発に活動していたバンドである。
当時のメンバーは以下の通りである。
・Phil May - vocals
・Dick Taylor - lead guitar
・Brian Pendleton - rhythm guitar
・John Stax - bass,harmonica
・Viv Prince - drums
ギターのDick Taylorはデビュー直前までRolling Stonesのメンバーであった人物というのは割と有名なエピソードである。諸般の事情によりStonesを脱退、自らが思い通りにできる音楽を模索して結成したのがPritty thingsである。後年のStonesの世界的な大成功と裏腹にPritty thingsの紆余曲折ぶりを比較すると、人間の「運命の分かれ道」をはっきりと認識させられてしまうのは否めない所。もしDick TaylorがStonesを辞めていなければ、大スターとしての道を歩んでいたのではないかと思うと、ちょっと切ない気分になる。
"Road Runner" Phil Mayの絶叫に等しいシャウトが強烈なインパクトを残す1曲目。ブルース・ハープの気怠いトーンと対称をなす通好みの選曲である。
"Rosalyn" Pretty thingsのデビューシングル。Dick TaylorのR&B指向が光る逸品。
"Unknown Blues" 初期のStonesに通じる渋〜いブルース。ギターとブルース・ハープだけで演奏される無駄のない荒削りな所が格好良い。
このバンドのアルバム、同世代のBeatles、Rolling Stonesのものに比べて明らかに録音状態が悪いのが非常に残念な点である。しかし、荒削りで鋭い演奏が聴ける所がPretty Thingsの魅力でありガレージ・パンクに繋がる系譜にあると言えるのかもしれない。Phil Mayの気違いじみたシャウトを織り交ぜたヴォーカル、Dick TaylorによるStones駆け出しの時代に叩き込んだR&Bの渋さ、といったものは60年代のブリティッシュ・ロックの中でもっと評価されても良い。